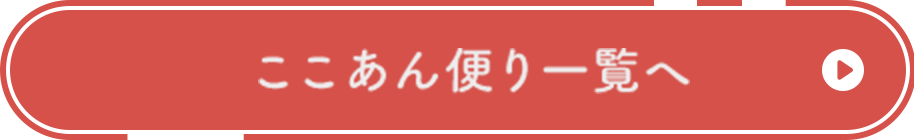ここあんのある上道界隈のことを、若い仲間がまちづくりのゼミで報告するのを聴きに出かけ、良き気分。
彼女の話を聴きながら、私たちが人との繋がりの中で生きていて、良き仲間と過ごす時間の豊かさを日々感じられることがどれだけ幸せなことかを改めて実感する機会となった。
良き仲間、良い人間関係とは、与えるもの、与えられるものが互いに等しい間柄をいう。
どんなに大切な人であっても、どちらか一方が与え、どちらか一方が与えられるというだけの関係性はいつか歪みが生じる。
こう考えると、お互いに等しく与え合える関係に恵まれるのは奇跡のようだ。
夫婦、親子であっても難しいことなのだ。
ところが、上道に集う人たちはまさに奇跡のような良き関係の仲間。
人間関係のストレスなし。
誰かが苦労しているときは助け、頑張っているときは応援する。
それを互いに当たり前のようにしている。
そして、自分に余りあるものは必ず分け合う。
得意なことは請負うが、得意じゃないことには手を出さなくて良い。
そして、それが仲間内だけじゃなく、外からやって来る人にも同じようにできてしまう素晴らしさ。
これが、上道ファンを増やし、気づけば文化的で豊かな環境になっている。
外からやって来る人たちと、こちらで受け入れる人たちは互いに楽しくて幸せな関係。
お世話する人、させる人みたいなことにはならないから。
こうした関係性が育まれた理由(わけ)を考えてみる。
やはり劇場(境港親と子どもの劇場)の存在が大きいだろうか。
苦楽を共にした長い時間のほとんどが楽しく、幸せで愉快だった。
「子どものため」という名目以上に、私は、私にとって仲間と過ごす時間がかけがえのないものだったし、みんながいれば何とかなると安心して過ごせた。
それは、今もその通りで、これから先の老後と呼ばれる時代を明るく照らしてくれる。
私は今、家とここあんを往復するだけの毎日で、外へ向かってコトを起こすことも少なくなっているけれど、すぐ近くで仲間が面白いことを思いついたり、外から訪ねてくる人が増えていることに、ただ身を委ねている。
気の置けない人たちと居心地の良い上道で、これからも愉快に暮らしていけるとしたら、それは素晴らしく幸せなことだと思う。

(写真は上道とは無関係、夫と出かけた旅の一枚。愉快な老後ってことで。)