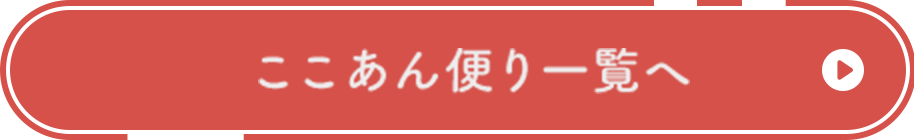わらべうたを歌うとき、人前で歌う場合に「正しく歌う」ことが求められるのだが、この「正しく」にいつも「?」な私。
この話をはじめると、ちょっとやっかいなので詳しく聴きたい方は、ここあんにでも話を聞きに来てもらうとして、今回は、「ああ、これがまさに正しく歌うってことだ!」って実感したことをお伝えしようと思う。
2012年、上道のおばあさん(聞き取り当時70代〜80代の上道在住ご婦人6.7名)に教えてもらったわらべうたが2曲ある。
もっと色々教えてもらったようにも思うけど、その後2曲を楽譜にして仲間と歌い続けている。
1つは、図書館でのわらべうたの会(季節ごと)のオープニングで使っている「♪あたまのうえに」という鬼きめの歌。
もうひとつは、「♪でるやでるでるばってん」という子ども同士が別れるときに使うわらべうた。
でるや でるでるばってん
でんけん こんけん こんけられんけん
こられられんけん こんけんな〜
この「♪でるやでるでる」は、長崎のでんでらりゅうば〜に似ていて、「ばってん」などはこちらでは使わない言葉だよな…
長崎から来た子どもが広めたのかな?
教えてくれたおばあさんたちの子ども時代に流行ったのかな?
そう思っていたのですが、先日のわらべうたの集まりで、「私、歌ってましたよ」という人が現れた〜。
知恵さんのYouTubeチャンネルをお見せすると、「優しい感じだね〜。私は、遊ばんよ!って、もっと厳しい(激しい?)感じで、♪来られられんけん、来んけんな!!」ってやってた、と実演して下さった。
遊びを断るときの歌だと聞いていたけど、なるほど、その実演を見て、あ〜、分かる!分かる!
子ども同士が大声で「来られられんけん来んけんな!」「来んけんな!」と言い合っている様子がはっきりと目に浮かんだ。
「こんけんな〜」と優しく歌うのではなく、「こんけんな!!」と強く言い切って歌ったんだね。
言葉だけで強く言い切ってしまうとケンカになりそうだけど、そうした言葉のやりとりを歌で表現し合うことで、遊びのひとつとして片がついたのだろう。
子ども同士のコミュニケーションにわらべうたが欠かせないものだったことが分かる。
この話を実演混じりで教えてくれたのは余子小校区のWさん。
境小校区のMさんは「来るや来る来るばってん…」と歌っていたと証言。
これこそまさに、わらべうたを正しく、だ。
結局のところ、わらべうたを「正しく伝える」(わらべうたの世界でよく言われる)など今や不可能に近いと私は思う。
子どもが、子ども自身の気持ちを歌に乗せながら遊べたとき、それがその人にとって正しいわらべうたであり、何より尊いのではないかしら?
だから私は、そのお手伝いができれば良いと思っている。
嬉しい、悲しい、寂しい、悔しい…、言葉にできない心の内を、歌に乗せて声に出して叫んだり呟いたりしながら、子ども時代を生きられたら、きっと次の元気に繋がるだろう。
私の子ども時代がそうであったように、今を生きる子どもたちにも、遊び呆ける時間がたっぷりあると良いなあ〜
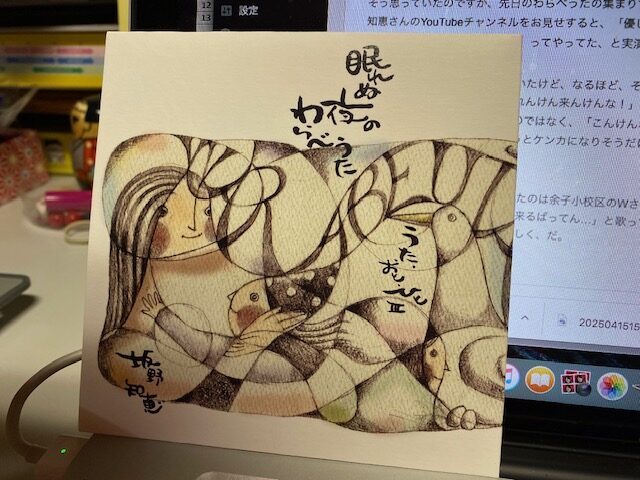
ふと、坂野知恵さんのCD「眠れぬ夜のわらべうた」(2016年7月)を聴きたくなって聴いていたら…
なんと!!
♪でるやでるでる(境港)が、♪でんでらりゅうば(長崎)とダブルで、それもibuki(ギタリスト)さんと一緒に歌ってるー
♪ゆきやこんこん(鳥取)も入ってた〜 素晴らし過ぎるCDだと、改めて感心しています。